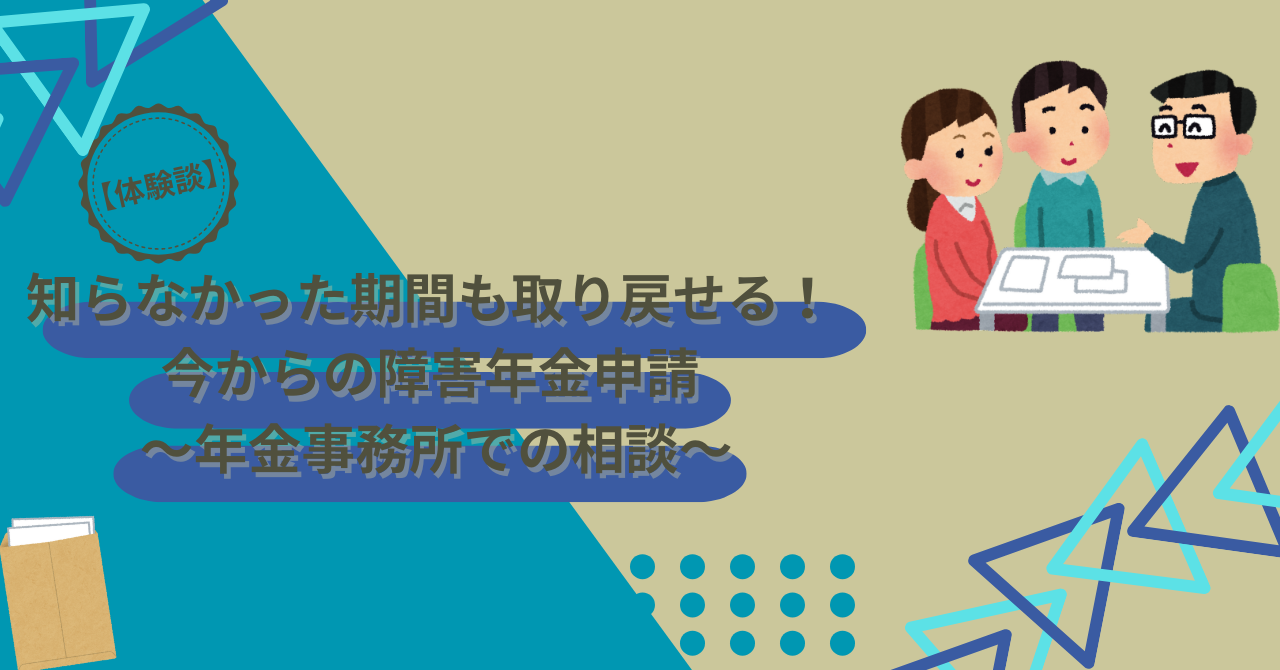■障害年金申請シリーズ
第1回:【体験談】障害年金申請への決意 〜グリオーマ患者の家族として考えたこと〜
第2回:【体験談】障害年金申請のスタートライン 〜初診日と保険加入について〜
第3回:【体験談】知らなかった期間も取り戻せる!今からの障害年金申請 〜年金事務所での相談〜(本記事)
準備を整えても、いざ申請となるとなかなか踏み出しにくいものですよね。
障害基礎年金の申請をするため、実際に年金事務所を訪問してどのような説明を受けたのか?
高次脳機能障害を伴う疾患で障害年金を申請した私たちの経験をもとにお伝えします。
特に印象的だったのは、申請から5年前まで遡って受給できる可能性があること。
私たちのように「障害年金という制度を知らなかった」という方も多いのではないでしょうか。
私たちが年金事務所で相談した経験を参考にしていただき、一歩を踏み出していただければと思います。
年金事務所訪問前の準備
まず、電話で年金事務所に相談の予約を入れました。
電話では、相談時間の予約と必要書類の説明がありました。
予約制になっているため、指定された時間に訪問することになります。
予約の電話では、以下のような説明を受けました
- 相談時に必要な持ち物(年金手帳、マイナンバーカードなど)
- おおよその相談時間(1時間程度)
持参したもの
前回の記事でお伝えしたように、初診日の特定は非常に重要です。
妻の日記には発作で救急搬送された日の記録があり、これが初診日の証明に役立ちました。
年金事務所での相談内容
相談時間は約1時間でした。予約制のため、待ち時間はほとんどなく、個室のような仕切られたブースで相談しました。
担当者は必要な書類の説明をしてくれました。
- 障害年金請求書(その場で記入例を見ながら作成)
- 診断書(病院で作成してもらう必要あり、指定様式)
- 初診日を証明する書類(カルテのコピーなど)
- 病歴・就労状況等申立書(生活状況や症状の経過を記載)
- 戸籍謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
- 年金手帳またはマイナンバーカード
大変だと感じたこと
- 申請書類は受付でその場でチェックしてもらえますが、不備があれば持ち帰って修正し再提出が必要です。複雑な書類もあるため、
何度も年金事務所に通うことになる可能性があります。 - 診断書の依頼から受け取りまでに時間がかかるため、全体的な申請プロセスの計画を立てておく必要があります。
残念だと感じたこと
審査のポイントについて具体的なアドバイスはほとんど得られませんでした。
「どのような点が重視されるか」という質問に対して、「専門機関で審査するので私たちにはわからない」という回答でした。
担当者は淡々と的確に説明してくれましたが、一般的な手続きの案内が中心で、個別の審査見込みについてはほとんど言及がありませんでした。
過去分の請求について
年金事務所での相談で最も驚いたのは、「障害年金は過去にさかのぼって請求できる」という情報でした。
私たちが担当者に「障害年金の制度を知らなかったんです」と正直に伝えたところ、申請時から最大5年前まで遡ってお金を受け取れる可能性があることを教えてもらいました。
「もっと早く知っていれば…」と思う方も多いと思いますが、知らなかった方にとっては大きな救いになる情報です。
私たちもこの話を聞いた時は、今まで知らなかったことが悔やまれる一方で、まだ間に合うという安堵感がありました。
遡及請求のポイント
担当者から説明を受けた内容をまとめると:
詳しくは障害認定日請求をご参照ください。
私たちの選択
妻のグリオーマの発症は2015年でしたので、相談時点では既に5年以上が経過していました。
担当者からの説明を受け、私たちは2つの申請を同時に行うことにしました。
- 遡って申請する方法:過去5年分を最大限さかのぼって申請
- 現在の状態での申請:現在の障害状態に基づく申請
この2つを同時に申請する理由は安全策を取るためです。
もし遡って申請する方が不受給になった場合でも、自動的に現在の状態での申請に切り替わるシステムになっているとのこと。
このように二重の申請をすることで、可能な限り受給の機会を確保できます。
注意が必要なのは、遡って申請するために過去の状態を今から証明するのは簡単ではないという点です。
私たちは幸い、妻が日記をつけていたので発症当時の状況を詳しく説明できました。
また、あまりにも過去の診断書を書いてもらうのはデータの保存期間から注意が必要です。
まとめ
初回の年金事務所訪問では、申請に必要な書類や手続きの全体像を把握することができました。
特に過去に遡って認定日請求ができる情報は大きな収穫でした。
私たちは申請にあたって社会保険労務士に依頼するかどうか迷いましたが、まずは自分たちでやってみようと決めました。
その理由はいくつかあります。
まず、「とりあえずやってみよう」という気持ちがありました。
社労士を介すると手続きが煩雑になる面もあり、シンプルに自分たちのペースで進めたかったのです。
また、正直なところ「自分たちが本当に障害年金を受給できる状態なのか」を試してみたいという思いもありました。
うまくいけば儲けもの、もしダメでも再申請できると割り切っていました。
ただし、不受給になった場合に不服の申し立て(審査請求)はできますが成功率は20%程度のようです。(参考:全国障害年金郵送申請サポート)
最初の申請で受給できるように慎重に行うことが大切です。
大きな金額になりますので、遡る期間が長い場合は社会保険労務士に相談することも検討した方が良いかもしれません。
専門家のアドバイスで受給の可能性が高まることもあります。
次回は、実際の書類準備と提出の体験についてご紹介します。
診断書と申立書の取得の方法や、アナログな手続きでの注意点など、手続き進めていった経験についてお伝えします。