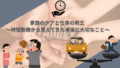障害年金申請シリーズ
第1回:【体験談】障害年金申請への決意 〜グリオーマ患者の家族として考えたこと〜
第2回:【体験談】障害年金申請のスタートライン 〜初診日と保険加入について〜
第3回:【体験談】知らなかった期間も取り戻せる!今からの障害年金申請 〜年金事務所での相談〜
第4回:【体験談】不受給から学ぶ障害年金診断書のポイント5つ(本記事)
障害年金申請には、医師による証明書類が不可欠です。
これらの書類は申請の成否を左右する重要な役割を持ちますが、その取得過程には意外な落とし穴があります。
私たち家族は必要な証明書類を揃えて申請しましたが、残念ながら不受給となりました。
この経験から学んだ「何が足りなかったのか」「どうすべきだったのか」という教訓をお伝えします。
障害年金を申請する方々が、私たちの失敗から学び、より良い結果を得られることを願っています。
診断書の種類と基本知識
障害年金の申請では、主に以下の医療証明書類が必要です。
- 受診状況等証明書:初診日を証明するための書類
- 障害状態を証明する診断書:障害の程度を証明する書類
これらが日本年金機構指定の特殊な様式なので年金事務所で受け取った書類を病院に提出して、診断書を書いてもらいます。
「日常生活能力の判定」という項目が認定の鍵を握ります。
診断書取得
受診状況等証明書の取得
私たちの場合、救急搬送された病院に電話をかけて証明書が発行できるか確認しました。
発症から5年以上経過していましたが、幸いカルテは保管されていました。
遠方の病院とのやり取りは約3ヶ月かかり、費用は約3,000円でした。
予想以上に時間がかかるので、余裕を持ったスケジュール管理が必要だと実感しました。
診断書取得の問題点
現在、通院している病院の窓口で「障害年金のための診断書をお願いします」と伝えました。医師と直接話す機会はありませんでした。
今思えばこれが不受給になった反省点です。
- 日常生活での具体的な困りごとを伝えられなかった
- てんかん発作の定義を意識消失だと勘違いし、頻度を正確に伝えられなかった
- 結果的に「日常生活能力の判定」が実態より軽く評価された
不受給から学んだ教訓
結果として「障害の程度が認定基準に達していない」という理由で不受給となりました。
不受給通知後、年金事務所に理由を詳しく聞き、社会保険労務士にも相談しました。
その経験から学んだ重要ポイントを5つにまとめました。
不受給から学ぶ障害年金診断書のポイント5つ
- 医師との直接コミュニケーションを取る
- 窓口だけでなく、診察時に主治医に直接「障害年金申請のための診断書です」と伝え、日常生活の困難さを評価することの重要性を説明しましょう。
- 日常生活の困難さを具体的にメモにまとめる
- 「何ができないか」を具体例で記録したメモを準備しましょう
- 料理中にガスの火を消し忘れる
- 服薬管理が一人でできない
- 複数の指示が理解できず混乱する
- 「何ができないか」を具体例で記録したメモを準備しましょう
- 症状を正確に把握して伝える
- 症状の定義や種類を医師に確認し、正しく理解した上で実際の頻度を伝えることが大切です。てんかん発作の種類や頻度など、専門的な事項は特に注意が必要です。
- 診断書を受け取ったらその場で内容を確認する
- 特に「日常生活能力の判定」欄を確認し、「できる」「ほぼできる」という評価が多い場合は、実態との乖離がないか確認しましょう。
- 疑問点があれば、その場で医師に質問や修正を依頼することが重要です。
- 専門家のサポートを早めに検討する
- 社会保険労務士などの専門家に相談し、診断書の書き方や評価の基準について詳しいアドバイスを得ることをお勧めします。
おわりに
これらのアドバイスは、私たち自身がまだ再申請の途中段階のものですが、不受給後に専門家から得た情報に基づく教訓として共有します。
特に高次脳機能障害のような外見からはわかりにくい障害の場合、その困難さを具体的に伝えることが決め手となります。
私たちはこれらの学びを活かして再申請を準備中です。
次回は「病歴・就労状況等申立書」の作成について経験をお伝えします。