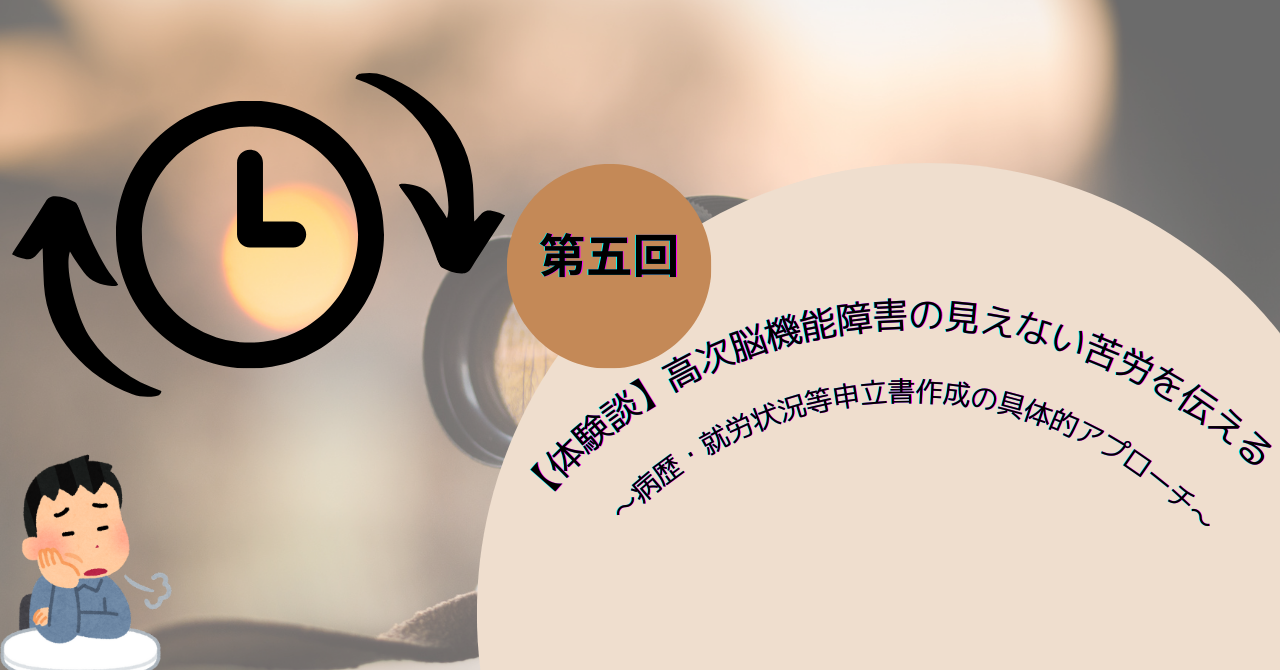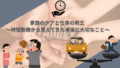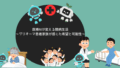障害年金申請シリーズ
第1回:【体験談】障害年金申請への決意 〜グリオーマ患者の家族として考えたこと〜
第2回:【体験談】障害年金申請のスタートライン 〜初診日と保険加入について〜
第3回:【体験談】知らなかった期間も取り戻せる!今からの障害年金申請 〜年金事務所での相談〜
第4回:【体験談】障害年金申請の書類作成と提出 〜グリオーマ患者家族の実体験〜
第5回:【体験談】高次脳機能障害の見えない苦労を伝える 〜病歴・就労状況等申立書作成の具体的アプローチ〜(本記事)
重要書類のひとつ「病歴・就労状況等申立書」についてです。
これは、患者自身(または家族)が作成する書類で、診断書だけでは伝えきれない日常生活の困難さを具体的に伝える貴重な機会となります。
特に高次脳機能障害のようなグリオーマの後遺症は、診察室の短時間では見えにくく、医師にも十分に理解されないことがあります。
申立書は患者の生活実態を伝える唯一の書類であり、審査結果を左右する重要性を持っています。
この記事では、私たち家族が実際に作成した申立書の体験と、不受給後に気づいた重要ポイントをお伝えします。
私たちの実際の記載内容
申立書には以下の内容を時系列に沿って詳細に記載しました。
特に重視したのは発症からの時間的経過と日常生活への具体的な影響です。
1.発症前から現在までの経過
- 初期症状の発現(てんかん発作の状況)から診断までのプロセス
- 治療の経過(手術、放射線治療、抗がん剤治療)とその影響
- 現在の状況(継続治療や定期検査の頻度)
2.高次脳機能障害の具体的な影響
- 記憶障害:買い物内容を忘れる、服薬管理ができないなど
- 注意障害:料理中のガスの消し忘れ、道に迷いやすくなったなど
- 遂行機能障害:段取りができない、簡単な料理の手順で混乱するなど
これらの記載では、抽象的な表現ではなく「〇〇しようとすると△△になる」という具体的な例を示し、生活の困難さをリアルに伝えるよう心がけました。
申立書作成のコツと工夫
1.AIの活用で作成の負担を軽減
時間的経過や日常生活への具体的な影響を考慮しながら長文を作成するのは非常に困難です。私たちはAIを活用して申立書の作成を進めました。
- まず要点をメモ程度に箇条書きで整理
- AIに「障害年金申請のための病歴・就労状況等申立書の文章作成を手伝ってほしい」と依頼
- 診断書の内容や実際の生活状況を入力し、適切な文章に整形してもらう
- AIの出力を基に家族で内容を確認・修正
AIの支援により、整理された文章で申立書を作成できただけでなく、「どのような情報が重要か」というポイントも整理できました。
ただし、最終的な内容の確認と修正は必ず自分たちで行いました。
2.時系列での整理を意識
- 発症前→発症→診断→治療→現在の状況、という時系列で整理
- 各段階での症状の変化や影響を明確に
- 日付や期間をできるだけ正確に記載
- 見出しや段落分けを活用して読みやすく構成
時系列で整理することで、病状の進行や生活への影響の変化が理解しやすくなります。
3.診断書との整合性を確認
- 初診日や治療歴の日付
- 症状の種類や程度の表現
- 日常生活の制限に関する記述
不一致があれば審査で疑問視される可能性があるため、診断書の内容を確認した上で申立書を最終調整しました。
診断書との連携の重要性
これらの申立書を作成する過程で私たちが経験した不受給を経て、社会保険労務士などの専門家に相談して得た重要な気づきがあります。それは、申立書と診断書の内容を連携させることの重要性です。
特に注目すべきは、申立書の「就労・日常生活状況」が、診断書の「日常生活能力の判定」と連動していることです。
私たちの場合は、振り返ってみると日常生活能力を「困難だが何とかできる」と控えめに記載してしまいました。
専門家からは「申立書は診断書を補強する役割がある」というアドバイスをいただきました。
診断書で「援助が必要」と評価されている項目については、申立書でもその具体的な状況を詳しく記載することで、一貫性のある申請書類となります。
私たちは再申請に向けて、この点を特に意識して申立書の見直しを行っています。
まとめ
申立書の作成は想像以上に時間と労力がかかりました。
高次脳機能障害があると書類作成自体が大きな負担となるため、家族の協力が不可欠です。
作成に苦労した申立書ですが、この作業を通じて私たち自身が「どのような困難があるのか」「どのようなサポートが必要か」を改めて整理できたことは、その後の生活支援にも役立つ作業だったと感じています。
申立書作成の5つの重要ポイント
1.具体的な症状経過を時系列で記録する
初期症状から現在までの変化を明確に
2.日常生活への影響を具体的エピソードで伝える
抽象的表現ではなく、実際の困難場面を描写
3.介助の必要性を明確に記述する
どのような場面で、どの程度の介助が必要かを具体的に
4.診断書との整合性を確保する
特に「日常生活能力の判定」との連動が重要
5.作成負担を軽減する工夫をする
AIツールの活用と家族での分担作業
障害年金の審査では、診断書と申立書を通じて「医学的な障害の状態」と「実際の生活上の困難」の両面から判断されます。
特に高次脳機能障害のような外見からはわかりにくい障害の場合、この申立書が審査結果を左右する重要な要素となりえます。
私たちはまだ再申請の途中段階ですが、不受給からの学びとして、これらの教訓を共有させていただきます。
次回は、申請後の流れと審査結果について、お伝えする予定です。