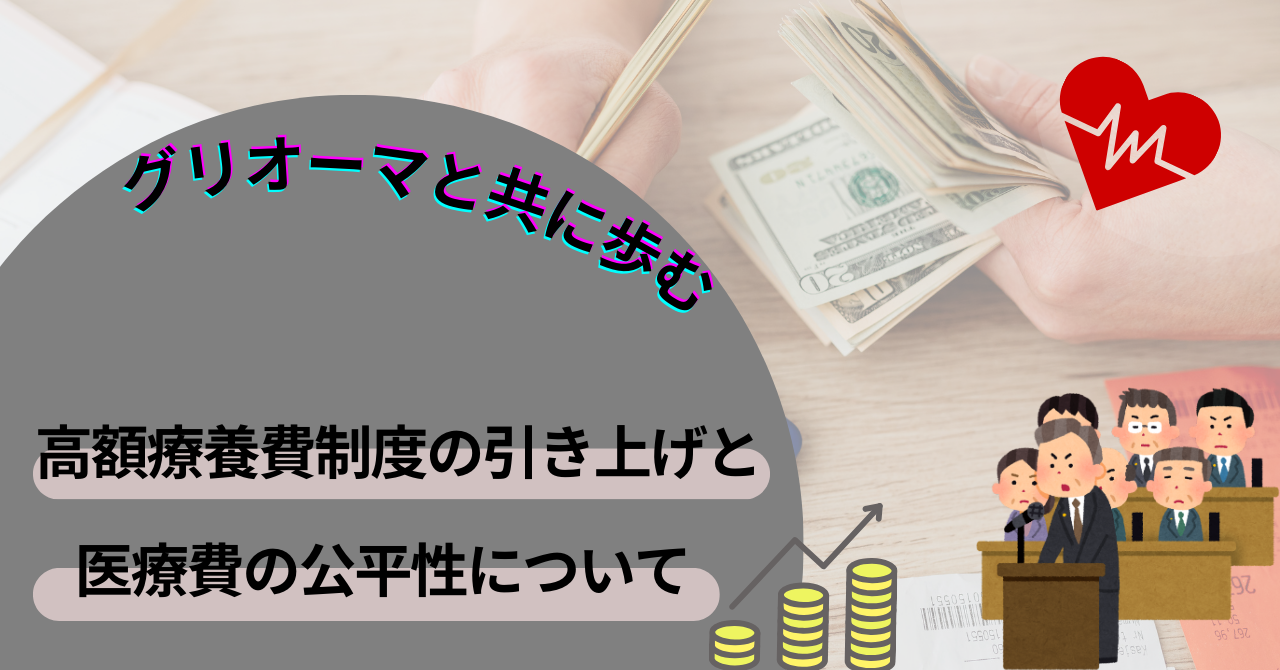高額療養費制度の負担上限額引き上げによるがん患者や難病患者の声が政策に反映され、見送る方針が固まりました。
脳腫瘍患者の家族として制度に支えられた経験と、医療系ITエンジニアとしての視点から、この決定の意義と「より良い制度のあり方」について考えてみたいと思います。
高額療養費制度の「心の余裕」
2015年、妻が脳腫瘍と診断された日、私の頭の中は真っ白になりました。
手術の必要性を告げられたものの、脳腫瘍は外見上の変化がなく、本当に手術を受けるべきか私たちは悩んでいました。
「見た目には影響を感じない状態なのに、頭を開く大きな手術が本当に必要なのか」
「手術のリスクと生活への影響はどうなるのか」
「2歳の子どもを育てながら、長期入院になった場合の生活はどうなるのか」
こうした不安の中、病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)から「高額療養費制度」の説明を受けました。
「月の医療費の自己負担には上限があります。手術や入院にかかる費用も、負担を抑えられます」
経済的な不安が軽減されたことで「受けられる治療は受けよう」と前向きに治療方針を決めることができました。
お金の心配をせずに治療に専念できる安心感。
これこそが、高額療養費制度がもたらした最大の価値でした。
妻は手術と2ヶ月の入院を経て退院し、実際に高額療養費制度を利用したのは脳腫瘍の切除手術の時のみでした。その後の定期通院では自立支援医療制度を利用しています。
もし高額療養費制度がなければ、私たちは経済的理由から必要な治療を躊躇したり、治療と家計の二重の不安を抱えたりしていたかもしれません。
両家の親からの支援を受けながらも、この危機を乗り越えられたのは、こうした制度による経済的・精神的支えがあったからこそです。
公平な社会保障を考える
医療費が増え続けているのは事実です。でも、その解決策として「病気の人の負担を増やす」という方法は本当に正しいのでしょうか?
私が思う公平な社会保障とは、「みんなが必要な時に助けてもらえる」仕組みです。
病気になった人だけに負担を求めるのではなく、社会全体で支え合う方法を考えるべきではないでしょうか。
例えば:
- 早めに病気を見つけて治療すれば、後から重症化して高額な治療が必要になるのを防げます
- 健康診断などで病気を予防すれば、医療費全体を減らせます
- 同じ検査を何度も繰り返したり、必要以上の治療を行ったりしないよう見直すことも大切です
患者さんの負担を増やす前に、医療の仕組み自体を見直すことで、医療費を適正にできる可能性があります。
誰もが制度を利用できる工夫
私が最も伝えたいのは、「知っている人だけが得をする」という今の制度の問題点です。
私たち家族が高額療養費制度を知ったのは、病院の相談員さんからの声かけがあったからです。
もし、その声かけがなかったら?制度を知らないまま、高額な医療費に悩んでいたかもしれません。
今の社会保障制度には、次のような問題があります:
- 制度を知らないと利用できない
- 申請の手続きが複雑で面倒
- 窓口に行く時間や体力がない人には負担が大きい
- 複数の制度があり、どれを使えばいいか分かりにくい
便利な仕組みで誰もが使いやすく
スマホで買い物ができる時代に、社会保障だけがアナログのままでいいのでしょうか?
便利で誰もが簡単に制度を利用できるような仕組み 技術的に実現可能です。
1. 自動でお知らせする仕組み
病院の窓口で支払った医療費が高額になったら、「高額療養費制度が使えますよ」とスマホにお知らせが届くような仕組み。わざわざ調べなくても、必要な時に必要な情報が届けば便利です。
2. 簡単に申請できる仕組み
マイナンバーカードを使って、スマホやパソコンから数分で申請できる仕組み。
窓口に行く必要がなくなれば、体力のない患者さんや忙しい家族の負担が減ります。
3. 最適な制度を教えてくれる仕組み
「あなたの状況では、この制度とこの制度を組み合わせると最も負担が少なくなります」と提案してくれる仕組み。複雑な制度の組み合わせを自分で考える必要がなくなります。
こうした便利な仕組みを作れば、「知っている人だけが得をする」という不公平をなくし、本当に支援が必要な人に適切に届く社会保障制度になると思います。
さいごに
高額療養費制度は、私たち家族が脳腫瘍との闘いを続けるための大きな支えとなってきました。
多くの患者家族にとって、「お金の心配をせずに治療に専念できる安心感」を提供する、かけがえのない制度です。
制度の持続可能性を考えることは重要ですが、それが「弱者への負担増」という形であってはならないと考えます。
IT技術を活用した情報格差の解消と、予防医療の推進による医療費の適正化。
これらを両輪として進めることで、より公平で持続可能な社会保障制度を実現できるのではないでしょうか。
病気や障害と向き合う人たちが、経済的不安なく治療に専念できる社会。
そんな社会の実現に向けて、私自身も経験を発信し続けていきたいと思います。